top of page
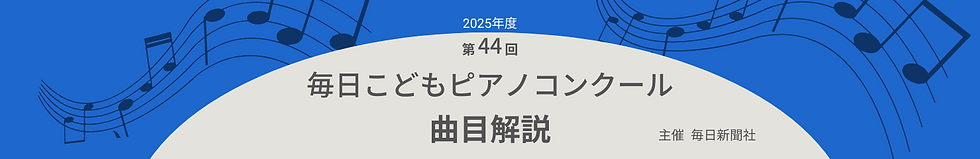
第44回の各部門について、課題曲・選択曲の曲目解説や、選曲に際してのアドバイスやコメントなどを、当番審査員の先生からお寄せいただきました。
当番審査員による曲目解説
幼児の部
若狭 玲衣 先生(当番審査員)

ピアノを始めて間もない幼児の皆さんには初のステージとなる方もいらっしゃると思います。
幼児期に大きなホールで演奏し、すばらしい響きを味わうことは、とても貴重な経験となるでしょう。あたたかい拍手や立派な盾も、これからの練習の励みになりますので、ぜひ大好きな曲で参加してください。
背伸びした曲を選ぶ必要はありません。手に合った、お子さんが心から楽しめる一曲で、舞台でのびのびと演奏してみましょう。
小学校1・2年生の部
木村 真由美 先生(当番審査員)

課題曲
メヌエット 114/115
3拍子の優雅な舞曲。2小節、4小節のまとまりでフレーズをよく歌い、右手のメロディーはもちろん、左手にも音楽を感じて、ノンレガートはバロックダンスの拍感を持ちつつ横の繋がりを感じて弾きましょう。
マーチ
アウフタクトで2分の2拍子、出だしからしっかり拍子感を持ちながら、生き生きと弾きましょう。特に左手の拍感が大切です。
スケルツィーノ
軽快な3拍子で拍感を持って、2・3拍目の連打は軽やかに音を揃えて。4分音符は弾みを持ちつつ、短くなり過ぎないように気をつけてましょう。
アリエッタ
歌を感じてなめらかに、2拍子、アンダンティーノなので遅すぎずに。小さなスラーに注意し8分音符は揃えてなめらかに弾きましょう。
選択曲
モーツァルト:アレグロ ヘ長調 K.1c
2拍子の軽快な曲、アウフタクトがとても重要な拍感を作り出します。同じメロディーは変化を出すと良いです。
ブルグミュラー:「25 の練習曲」1~11番より 1曲
それぞれに題名があり、子どもたちが想像しやすい曲が揃っています。アーティキュレーションに注意してその曲の情景やイメージを大切に演奏しましょう。
クラック:魔女のおどり Op.4-2
魔女の踊りという不気味な感じを出しながら、3拍子は大きく1小節1拍に感じて。16分音符は転ばないようによく揃えて弾きましょう。
グレチャニノフ:さようなら(別れ)Op.98
2小節で応答するフレーズは歌ってなめらかに。左右の音はよく聴いて揃えてバランスよくハモらせてください。
外国の曲:タランテラ
タランテラはテンポの速い踊りの曲で、大きな2拍子で生き生きと。右手8分音符は転ばないように、左手和音は拍を感じてキリッと。最後は低音から次第にクレッシェンドしてかっこよく決めましょう。
ギロック:おばけの足あと
ゆっくりとていねいに、強弱ははっきりと。どこからかおばけの足音が聞こえてくるような、ちょっと怖い雰囲気を想像しながら弾いてみましょう。
ギロック:アラベスク・センチメンタル
長いフレーズで左から右に受け渡す音型はなめらかに。中間部は音が動き、手の交差もあり難しいので、なめらかに弾けるようにゆっくりと音を聴いて、流れに音を乗せるようにまとめましょう。
バスティン:メキシコの祭り
勢いのある前奏と後奏はリズムに乗ってくっきりと。中間の歌の部分はテンポが変わりますが、遅すぎず長いフレーズで、左手の和音は軽やかに。最後はかっこよく決めてください。
平吉毅州:北国のおはなし
語りかけるように右手のメロディーは指くぐりなどに気をつけてなめらかに、左手4分音符のスタッカートは右手の流れに合わせてあまり鋭くならないように、中間部は調性の変化も意識して演奏しましょう。
轟千尋:おつきさまのはなし
やさしい気持ちでお話しするように、右手はなめらかに、左手の和音は右手のメロディーをよく聴いて、ハーモニーや調性の変化にも耳を傾けて表情豊かに演奏しましょう。
安倍美穂:よなかのとけい
左右のスタッカートはリズムを感じてくっきりと。テヌートの音や和音は楽しそうに。時計屋さんの色々な時計が夜中に正確に刻んでいる様子を想像してみましょう。
小学校3・4年生の部
工藤 真樹子 先生(当番審査員)

課題曲
インヴェンション 1番
素直な抑揚で、どの様にテーマが変化発展してゆくのかを追いかけて。楽しい会話が聴こえてくるはず。左右が16分音符になる部分は音楽の濃いところ。気持ちも音色も濃く。最後はワクワクしながら音楽の高みに登って終わりましょう。
インヴェンション 8番
1オクターブを跳躍しながら一気に登るテーマからこの曲の活発なキャラクターが読み取れます。その後の16分音符でなだらかに降りてゆく部分との対比をいつも楽しんで弾きましょう。
小プレリュード ホ短調
ホ短調という調性が緊張感を感じさせます。分散和音からなるテーマはイキイキと活発に。変化の多い曲です。場面ごとのニュアンスを細かく設定し、変化を楽しんで表現してください。
小プレリュード ハ長調
鳴り響くバスの主音から始まる堂々とした雰囲気。ハーモニーの流れを感じて。テーマの分散和音を弾く時は、しっかり指を広げて、手首の回転を使いながらおおらかに弾きましょう。
ジーグ
ジーグは、速い3拍子の舞曲で、跳ねるようなリズムが特徴です。バロック時代の華やかさと軽快なリズムが魅力の一曲。6/8を二拍子に捉えて軽やかに弾くと曲の魅力が引き立ちます。スタッカートは引き締まった指先で弾きましょう。
メヌエット
メヌエットは、宮廷で踊られていたゆったりした3拍子のダンス。貴族がドレスや燕尾服を着て、優雅にステップを踏むイメージで弾いてみましょう。 2小節1フレーズに、素朴なメロディーのまとまりを意識して弾きましょう。
インパーティネンス
カノンから始まるこの曲は、ポリフォニーを経験するのにとても良い曲です。左右どちらかの音楽が疎かになる事のない様に。調やハーモニーの変化を追いかけて説得力ある演奏に仕上げましょう。
選択曲
作曲家の個性、時代、様式などを捉えて難易度ではなく、生徒さんの良さが充分発揮できる曲を選曲しましょう。
クーラウ:ソナチネ ハ長調 Op.55-3 第1楽章
いろいろな楽器がソロで、トゥッティで合奏している様子を想像しながら生き生きと弾きましょう。
スピンドラー:ソナチネ ハ長調 Op.157-4 第1楽章
はっきりとした音形が特徴です。ここでは、明快なタッチとしっかりとしたリズム感が必要。展開部(中間部分)では短調の雰囲気が加わり音楽が変化します。表情の変化を意識しニュアンスをつけることが大切です。 スタッカートとレガートを対比させて。
ブルグミュラー:「25 の練習曲」9~25番より 1曲
ブルグミュラーはテクニックの習得と表現力の両方が叶う曲集です。各曲のタイトルからイメージを膨らませ、構成を考え表情豊かに立体感のある演奏を目指しましょう。
ショパン:ワルツ イ短調 遺作
哀愁漂う美しいワルツ。息遣いを大切に1フレーズを一息に歌いましょう。左手2.3拍目の和音のタッチを丁寧に。ペダルも工夫して繊細に踏みましょう。
グルリット:狩の曲
狩りの情景を表現した力強く勇ましい曲です。はっきりとしたリズムと勇ましいメロディーが特徴で、まるで馬に乗って森を駆け抜けるような雰囲気があります。fとpの対比を分かりやすく。躍動感のある演奏を目指しましょう。
リュバルスキー:やさしい歌
胸に沁みる一曲です。左右のメロディーをよく歌わせて、温かさと優しさが感じられる様に弾きましょう。レガートと左右のバランスを意識して。
ギロック:手品師
スタッカートとレガートの対比、突然の転調や音の跳躍など、予想外の音の動きが、まるでマジックのよう! 軽快なテンポをキープしながら、リズムの遊び心を表現しましょう。
平吉毅州:赤い月とこびとの踊り
タイトルの「赤い月」は夜空に浮かぶ不思議な月、「こびとの踊り」はその下で楽しげに踊る小さな妖精たちをイメージさせます。スタッカートは指先引き締めて、歯切れの良い音で。中間部はペダルも上手に取り入れて。
安倍美穂:たいまつの踊り
燃え上がるたいまつの光の中で、情熱的に踊る人々の姿をイメージさせる、エネルギッシュでダイナミックな作品です。3+2の拍子に乗ってアクセントを楽しみつつフォルテとピアノの差もはっきりとつけましょう。
名田綾子:粉雪のファンタジー
優しく繊細な旋律と、澄んだ響きが印象的で、まるで雪がキラキラと舞い落ちる様子をピアノで表現しましょう。軽やかで繊細なタッチを意識して透明感のある音を目指しましょう。メロディーは流れるように、なめらかなレガートで弾くと幻想的な雰囲気が生まれます。
小学校5・6年生の部
渡辺 郁子 先生(当番審査員)

課題曲
インヴェンションより 1曲
バッハが序文で述べているように、二声を綺麗に弾き分け、歌わせ、主題の展開にも目を向けてみましょう。
シンフォニア 11番
各声部の重なりによってできる美しいハーモニーを感じながら、大きなハーモニーの流れや方向性を捉えてみましょう。
フランス組曲 2番 エア
対話風の美しい二声の旋律は、拍感を大切にしながら、横のラインを感じ、大きなまとまりで歌いましょう。
フランス組曲 5番 ガヴォット
明るく躍動感のある曲。アウフタクトは踊りを意識して、2拍目裏から1拍目の間は空中、1拍目で着地する感じを表現してみましょう。
プレ・インベンション 25番 ブレ
ブレの特徴である2小節目、4小節目にある右手のシンコペーションは、左手のカノンの表現とともに、しっかりと3拍目を感じましょう。
選択曲
ラモー:タンブラン
クラブサン(チェンバロ)のために書かれた曲。軽くはっきりとした細めの美しい音を思い浮かべて、フランスの民俗的な太鼓(タンブラン)を使った舞曲を捉えてみましょう。
モーツァルト:ソナタ K.545 第1楽章
「初心者のための小クラヴィアソナタ」と記された愛らしい曲ですが、アルベルティバス、アルペジオ、スケールなど基礎的なテクニックを学べる要素が多くあります。美しく弾けるように耳をしっかり使いましょう。
フンメル:スケルツォ
ユーモアを持って明るく軽快に。8小節まとまりのフレーズはそれぞれ方向性を考えて曲想を考えましょう。
ブルグミュラー:「18 の練習曲」より 1曲
ピアノ教師としてのブルグミュラーの目線が生かされたエチュード集。それぞれの曲の性格を考え、その表現のためのテクニックを身につけていきましょう。
メンデルスゾーン:ベニスのゴンドラの歌
さざ波のような緩やかな揺れを感じる伴奏と美しい旋律は音色の違いやバランスに気をつけながら、フレーズを考えて表現しましょう。
ドビュッシー:グラドゥス・アド・パルナッスム博士
クレメンティのエチュードの単調さを皮肉った曲ですが、至る所にドビュッシーの魅力的な響きが散りばめられています。細かな強弱のニュアンスやハーモニーの色合いも表現してみましょう。
ショパン:ワルツ ホ長調 遺作
重音、オクターヴ、跳躍や音域の変化など、ピアニスティックな魅力をワルツのリズムにのせて生き生きと表現しましょう。
メリカント:ワルツ・レント
歌曲で知られるメリカントですが、この曲も歌のような美しい旋律とハーモニーで書かれています。表示記号を大事に読み取り、肉声の温かさや呼吸を感じて弾きましょう。
秋元恵理子:夏の夜の流星群
美しいハーモニーで書かれた上から下に、まるで星が降ってくるかのようなアルペジオは耳を澄まして、2小節まとまりのメロディーを歌いながら、透明感、煌めきのある音で弾きましょう。流星群の多彩な光景を想像を膨らませて表現してみましょう。
三善晃:波のアラベスク
常に動いている波の持つ様々な表情を視覚的、聴覚的に想像しながら、力強さ、繊細さなど曲想を考えてみましょう。
中学校の部
棚瀬 美鶴恵 先生(当番審査員)

課題曲
バッハは対位法的なもの、バロックダンス、器楽的なもの、そして宗教的な歌など様々な要素を持っています。ピアノ以外の曲に沢山触れて幅広い感性を持ちましょう。
シンフォニアより 1曲
3声を弾き分けることは勿論大切ですが、それを聴き分ける多声音楽への入り口として勉強して頂きたいです。
平均律 1巻 2番 フーガ
弦楽合奏の柔らかなピッチカート奏法等もイメージをして、軽やかなリズムの中にも短調の深い味わいと厳格なリズムの正確さを大切に。
平均律 1巻 21番 プレリュード
トッカータ風の生き生きとした輝きのある曲です。フランス風の付点の和音の表現も魅力的に。
フランス組曲 3番 アルマンド
優雅なバロックダンスを見てイメージをつかみましょう! 左右の表情豊かな音の動きを美しい流れになるように表現しましょう。
フランス組曲 6番ジーグ
大胆に動く軽やかで華やかな音の動きをつかみましょう!歯切れよくジャンプするダンスのステップを感じましょう。
選択曲
ハイドン:Hob.XVI/34 ホ短調 第3楽章
ロンド形式で書かれています。ホ短調→ホ長調に変わる転調を鮮やかに表現できるようにしましょう。
ベートーヴェン:「テンペスト」第3楽章
16分音符の流れがただ流れ去るのではなく、息のつまるようなベートーヴェンの心も掴んで表現してほしいです。
ショパン:ワルツ Op.69-1
半音階で始まる旋律が大変魅力的です。途中マズルカ風のリズムの特徴も出しましょう。ワルツは左手の表現がもっとも重要です。
リスト:12の練習曲 第9番
大変美しいメロディと装飾的な要素が特徴で、ロマン派を勉強する入り口としてとても魅力的な曲です。
グリーグ:「ホルベアの時代」より 1. 前奏曲
大変勢いのある輝かしい曲ですが、その中に北欧らしい叙情性を感じて表現してほしいです。
シベリウス:樅の木
北欧にとっての樅の森は永遠の生と死の象徴ですが、自然を愛する民族性を活かしてインスピレーション豊かに演奏してください。
バルトーク:オスティナート
激しく連打される和音の上に民謡が歌われます。様々な民族楽器を想像しながらリズムも明快に。
ショスタコーヴィチ:「3つの幻想的舞曲」Op.5-1
タイトルの通りとても幻想的で色彩豊かな不思議な曲です。音の高低さを素敵に彩って表現を楽しんでください。
中田喜直:風の即興曲
淀みなく続く3連符を即興的な風の動きと重ね合わせて、レガートで音の方向性を感じて爽やかな空気感を出しましょう。
関向弥生:リズミックダンス
目まぐるしく変わる拍子とアクセントの位置、くるくる変わる和声の変化が特徴的です。ポリリズムのようなどこかエキゾチックなところも魅力です。
高校の部
松原 寄美子 先生(当番審査員)

バッハの平均律クラヴィーアは長調、短調24の調性を網羅したどの曲も美しいハーモニーを奏でる曲ばかりです。
曲の選択の時も、練習の時もできるだけ沢山の曲を聴き、楽譜を読み想像力を膨らませて取り組んで下さい。
選択曲は、せっかく長い時間をかけて学ぶのですから「演奏したい曲」「学びたい曲」「自分を生かせる曲」などいろいろな観点から選んでみて下さい。
楽譜の向こう側にある作曲家の想い、人生、その時代の文化等にも興味を持ち説得力のある演奏を目指してください。
連弾の部
若狭 玲衣 先生(当番審査員)

ピアノの先生に「メロディも伴奏もよく聴きましょう」と教えて頂いたことがあるでしょう。演奏する上で、各声部をよく聴いて美しい響きを作ることは、とても大切です。
連弾に取り組むと、自然とお互いのパートを聴き合い、バランスを考える力が身につきます。
そして、お友達や兄弟で一つの演奏を作り上げるのは本当に楽しいです。魅力的な曲もたくさんあります。
どうぞ連弾部門への参加を通して、アンサンブルを楽しんでください.
bottom of page















